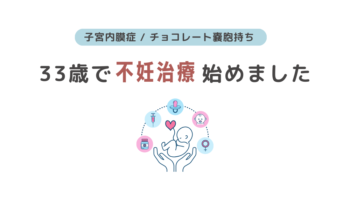わたしは「産後うつ」「不安障害」と診断され、生後8ヶ月の頃から息子を保育園に預かっていただいていて、今は精神科に通い服薬をしながら専業主婦をしています。
働いていないのに子どもを保育園に預けることに対して、よくない感情を持つ方もいるかもしれません。
わたし自身も「こんなことで子どもを預けるなんて母親失格だ…」「働きながら家事育児をしている人はたくさんいるのに…」と、それが出来ない自分が本当に情けなくて申し訳ない気持ちが今でもあります。
でも今は市の保健師さんや保育園の先生、病院の先生にもアドバイスをもらいながら、なんとか生活していけています。
今回はわたしが「産後うつ」「不安障害」と診断されるまでのことや、それからのことを書いていこうと思います。
産後うつの始まり?
わたし自身が自分の様子がなんとなくおかしいなと思い始めたのは、産後1ヶ月くらいのことでした。
- 訳もなく涙が出る
- 息子が泣くのが怖い
- 息子と2人きりになるのが怖い
- 里帰りから帰るのが不安で、里帰りを終えられない
でもこういった産後の症状はホルモンバランスの乱れで誰しもが経験する可能性がある「マタニティブルー」かもしれないとも思っていました。
この頃はとにかく寝不足で頭が回らない、息子のことで手一杯で他のことが何も出来ませんでした。
里帰りはしていましたが、家族全員が働いていたので基本的に夜中の対応は全てわたし1人でしていました。
夜中の授乳、授乳しても泣き止まない息子、生後3週頃からは夜もなかなか寝てくれないことも多く本当に寝不足と孤独でどんどん不安がいっぱいになっていきました。
この「眠いのに眠ることが許されない」「わたしがやるしかない」という状況が、今思うと「産後うつ」「不安障害」への始まりだったんじゃないかなと思います。
生後4ヶ月健診。育児は楽しいか?「いいえ」
わたしは産後うつの症状が酷くなって、親身になって下さったのは市の保健師さんだったのですが、保健師さんと関わるようになったきっかけは、息子の生後4ヶ月健診での問診で「育児が楽しいか?」という質問に「いいえ」と回答したことからでした。
(産後の自宅訪問も生後2ヶ月半くらいの時にありましたが、その時は当たり障りなく終わりました。)
うちの市の4ヶ月健診は小児科でやってもらうんですが、問診票にこの答えがある人は全員、市に連絡がいくことになっているそうです。
ただわたしは最初の頃はあまり保健師さんに心を開いていなくて、電話をかけてきてくださっても出ないことの方が多かったです。
今ではとても申し訳ない話ですが、「どうせ話聞いて終わりなんでしょ?」と思っていたからです。
助けてくれる訳じゃないなら、そういう気休めで必要ないと思ってました。
息子が生後4か月の頃は「楽しい」なんて感情は一切なかったと思います。
1日1日がとにかく長くて、孤独な毎日でした。
今でも思うのが「育児が楽しいか?」という質問で「はい」と回答できる人ってどれくらいいるんだろう?楽しいだけで育児できる人なんているんだろうか…
息子と2人きりでいると苦しくて息ができなくなる
そして息子が4ヶ月の頃から、目に見えて自分の体調がおかしくなっていたのを感じました。
夫は毎日仕事で帰りが遅くワンオペ状態。
そして夜中の授乳(この頃はもう完ミでした)でも、起きてはくれない夫。
そして息子が何と言ってもすごい抱っこマンで、昼間は全く床に降ろすことが出来なかったんです。
この頃寝返りするかしないかくらいの時期でしたが、本当に寝転がるのが嫌いなのか、昼間は布団の上でもプレイマットの上でも、なんならオムツ変えでも、とにかく寝転がすと泣く子でした。
もちろんお昼寝も抱っこ。
そういったこともあり、わたしは体力的にも限界に近く精神的にもかなり参っていました。
そしてある日の朝、夫が仕事へ行ってからすぐ息子と2人きりになって、急に息が苦しくて動悸もして涙が止まらなくなってしまいました。
夫には息子といるのが辛いという話は何となくしていましたが、あまり理解してもらえていなくて結局わたしがその時頼ったのは両親。
そして息子が生後4ヶ月の頃また、1ヶ月ほど実家にお世話になることになりました。
精神科の初診予約が2ヶ月後
息子が生後4ヶ月でまた実家に戻ることを選択し、夫とは完全別居状態でした。
わたし的には何もしてくれない夫といる家より、少しでも息子と2人でいる時間が少なくなる実家の方が安心できました。
そしてこの時から精神科の受診を考えるようになり、自宅から通えそうな病院を探して予約の電話をしました。
しかし初診予約はいっぱいの状態で、1ヶ月先になることを伝えられました。
日にちは決定できず、空きの順番が近くなってきたら病院の方から連絡があるという感じでした。
その時はもう何でもいいからとりあえず予約だけはしておこうという思いでした。
他にも探せば違う病院はあったかもしれませんが、そんな気力も当時はもうなかったです。
この時1ヶ月くらい先だと言われていましたが、実際に初診に行けたのは2ヶ月先でした。
今精神科や心療内科は患者さんが多く、初診までに時間がかかってしまうことはよくあることみたいです。
2回目の里帰り。自分の居場所がない
2回目の里帰り期間も、母には家事全般をしてもらい、わたしはひたすら息子のお世話をすることで手一杯。
そして息子と2人きりでいると、泣き止まない時に思わず息子に手をあげてしまうことがありました…。
誰かがいてくれればそういうことはしない。そんな自分自身が怖かったです。
でも誰かがいてくれる安心感はありましたが、現状が何も変わっていないことに更に不安が増していました。
そして息子が泣くことで家族に迷惑をかけていると思い込んで実家にいても、気を張って生活していました。
- わたしはいつまでこうして実家に頼っているんだろう。
- 息子は比較的夜は寝るようにはなっているけど、夜中2〜3回起きる。夜中の対応の孤独感はいつまで続く?
- 日中の永遠抱っこ、お昼寝も抱っこ。このままじゃ育児以外はできないまま?
- 本当はこれ以上両親に迷惑かけたくない。
- 息子が泣いたら泣き止ませなくてはと思ってしまう。
両親にはとても迷惑をかけていると思っていて、息子と2人きりでの不安を和らげるために実家に戻っていましたが、「早く自分の家に帰って1人でなんとか出来るようにならないと」と思うようになり、「きっと迷惑だと思われている」「息子が泣いたらうるさいと思われるからなんとかしないと」と思い、家族の顔色を伺って過ごすようになりました。
それがだんだんと大きくなって、結局実家にいても自分の家にいても心が安心できる時がなくなってしまいました。
両親もわたしが実家にいることは大丈夫だけど、このまま夫と別居状態で「夫婦」としては大丈夫なのかというのを心配していたみたいです。
結局何かが解決したわけではなかったですが、1ヶ月ほどでまた自分の家に戻ることになりました。
保健師さんに助けを求める
家に帰ってからも結局わたしの体調はよくなることはなく、泣きながら夫に仕事に行かないでくれと頼み込むようになり、見かねた夫は仕事を休んでとりあえずどこでもいいから、すぐにでも診てもらえる心療内科を探してわたしを連れて行ってくれました。
そこは内科メインの心療内科でしたがでもとても良い先生で、わたしが泣きながら話す内容をしっかり聞いてくれました。
「心療内科」よりも「精神科」でしっかり診てもらった方が良い。でも今精神科はどこも初診の予約はかなり待つとこばかりだと思うから、精神科の受診ができるまでうちで抗うつ薬を処方するね、と言ってくれました。
こうしてまずは服薬が始まりました。
あの時ちゃんと話を聞いてくれて対応してくれた心療内科の先生には本当に感謝です。
ただ抗うつ薬はすぐに効き始めるわけでもないので、ここからも息子のワンオペ育児には不安と恐怖ばかりでした。
そんな時に助けを求めたのが市の保健師さんでした。
息子の4ヶ月健診の頃から何度か電話をくれていて、わたしはほとんど出ないことの方が多かったけど、それでも定期的に連絡をしてくれていました。
そしてわたしは泣きながら保健師さんに「助けて欲しい」と伝えました。
その言葉が出たのはもうどうしたら良いのか自分ではわからなかったから。
率直に「息子をどこかに預けたりすることはできないか」と聞きました。
保健師さんは今どう言う対応が出来るかすぐに確認してくれ、1番最初に考えてくれたのは「一時預かり保育」。
保健師さん自身が一時預かりを実施している保育園に直接何箇所か電話をして確認してくれました。
ただ当時は1月ということもあり保育園自体に空きがなく、特に0歳児の一時預かりは予約でいっぱいで、利用することが出来ませんでした。
それでも保健師さんは他の方法を探してくれて、次に提案してくれたのが「産後ケア」でした。
出産後、体調や育児に不安のあるお母さんが安心して子育てができるよう、お母さんと赤ちゃんの心身のケアや育児サポートなどが受けられる事業。
市によって利用に助成が出ることがあります。()内は当時の助成が出てのうちの市の利用料
現在確認したら宿泊型が8,500円に値上がりしてました(´・・`)
- 宿泊型(6,500円)
- 日帰り型(3,500円)
- 訪問型(2,000円)
宿泊型、日帰り型だとご飯が用意してもらえたり子どもを預けたりして休むことが出来ます。
※利用内容や金額は病院や市によって違います。
産後ケアは息子が生後2ヶ月の頃に出産した病院で数回利用したことがありましたが、そこの病院では寝返りが出来るようになった子だと利用が出来ませんでした。
息子はその時もう6ヶ月だったので無理なんじゃないかと思ったのですが、保健師さんは違う病院であれば大丈夫なところもあるからと、これまた保健師さん自身が問い合わせてくれました。
そして泊まりはできないけれど、託児所があって生後6ヶ月でも昼間なら預けることができる産婦人科があるので、そちらを利用してみたはどうか?と勧めてくださり、最短の日にちで予約も取っていただきました。
その時の保健師さんは本当に本当に親切で、少しでもわたしが子どもと2人時間を少なくて済むように考えてくれました。
わたしの夫の仕事がシフト制ということもあり、「旦那さんのお休みは次いつですか?」「だったらこの日も産後ケア利用しませんか?」など、とにかく細かくわたしの身の回りのことを把握しようと努力してくださっていました。
時には、今近くを回っているのでお家にお伺いしてもいいですか?と家にも来てくださったり、わたしがいつも夕方の息子のくずりタイムがとてもしんどいという話をしたら、毎日のように夕方に電話をかけてくれたりもしました。
もちろん、わたしが息子に手をあげてしまう話も聞いてくださり全く責めることもありませんでした。
そして自宅に来ていただいた時に、初めて「一時預かり」ではなく、「保育園に通わせることを考えてみませんか?」と提案して下さいました。
精神科に受診出来たら、先生に意見書を書いてもらえれば保育園に預けることができます、と。
その頃、時期的には1月末で途中入園もできなくはなかったですが、空きが限られている状態でした。
とにかくまずは精神科の受診待ち。それまでは産後ケアや両親などに頼る形でなんとか生活していきました。
産後うつ、不安障害と診断される
精神科の予約をした11月末から2ヶ月が経とうとした頃、ようやく受診することができました。この頃息子は生後6ヶ月頃でした。
そしてここでようやく「産後うつ」と「不安障害」と診断されました。
息子を保育園に預けることを市の保健師さんに勧められていることをお話ししたら、入園手続きに必要な意見書もすぐに書いていただけました。
さらに病院では自立支援医療の申請も勧められました。
精神疾患の治療はいつ治るかの見通しがなく、医療費の負担を少しでも少なくした方が良いという先生からお話しでした。
市に申請することで、今の精神科での支払い(お薬代も)は1割負担で済んでいます。
保育園入園手続きで挫折しそうになる
ようやく精神科を受診できたことによって、保育園入園に必要な「医師の意見書」をもらうことができました。
保健師さんからは私の症状から当時2月初旬で、3月からの途中入園も勧められていて、わたしもとりあえず出来ることなら早めにと考えていました。
ただ「うつ状態」のわたしにとって、入園手続きを進めること自体がとてもしんどくて、保育園見学なんていけるはずもなく、全然頭が回らない状態で少しのことで頭がパンクしそうになってどんどん気持ちがしんどくなってしまいました。
- 何をどうしたらいいか考える事ができない。
- 決断ができない。
- すぐに疲れてしまう。
空きの少ない中、保育園を選ぶということも自分で判断できず、保健師さんにも泣きながら相談しました。
そして4月入園の2次募集なら3月頭までの期限があるからそれを目指していこうという話になりました。
もちろん2次募集は先着順になってしまうので、のんびりはしていられませんでしたが、幸い4月入園だと息子は0歳児クラスになるので、空きがある園が途中入園より多くありました。
そしてわたしはあまり多くの園に見学へ行く気力もなく家から1番近い保育園にだけ見学に行きました。
見学には夫もついてきてもらい、そのままその園に入園を決めました。
その園は0歳児は15人の定員で、4月入園の時点で8人空きのある状態でした。でもその後6月頃には定員いっぱいに埋まっていたので、当時はちょうど空きがあって本当にラッキーだったなと思いました。
今現在のわたしと息子
生後8カ月から保育園に通いだした息子は今1歳2ヶ月になりました。
わたしは変わらず定期的に精神科に受診をして服薬しながら息子を保育園に預けて生活しています。
正直息子の保育園入園が決まってからは、本当にこれでよかったのかな?息子にとっては可哀想なことをしてるんじゃないかな?という思いがいっぱいで、息子の保育園のことを考えるだけで何が正解か分からなくて、何故か悲しい気持ちでいっぱいでした。
そしてわたしは息子が可哀想なんじゃないかという不安と、もう一つ違う不安あったんです。
それは保育園に入り今までと生活リズムがガラッと変わることで、「息子がもっと夜寝なくなってしまうのではないか」「朝保育園に連れて行って泣き喚く息子の姿を見て自分のメンタルは持つのだろうか」「もっと大変になるんじゃないか」とそんな不安まで頭によぎっていました。
これは病院の先生によると予期不安で、起きてもないことをずっと考え頭から離れなくなってしまう不安障害の症状の一部でもあるみたいでした。
息子に申し訳ない気持ちもありながら、自分自身の保身のことも考えてしまっていました。
しかしそんな心配もよそに、息子は楽しそうに保育園に通ってくれています。
慣らし保育の頃から、朝わたしと離れる時に泣く事なく保育士さんに抱っこされました。
わたしはそれだけで安心して息子を保育園に預ける事ができました。
そして息子と離れる時間を持つ事で、少しずつですが落ち着いて生活できるようになってきています。
夜泣きに関しても保育園に通いだしても、夜に起きることも少なくなってきていました。
わたしの中では育児で眠れないことが1番ダメージを受けていました。
もともとロングスリーパーということもあり、息子の夜泣きで眠れないことの恐怖心が人一倍あったと思います。
精神科を受診してからは、基本的に夜中の対応は夫がしてくれるようになりました。
息子自身も夜中に起きても1回、多くて2回くらいにはなっていたので、眠れないことの恐怖心を理解してくれた夫は、今でも基本的に夜中の息子に関することは対応してくれています。
保育園から帰宅後は基本的には今まで通り寝かしつけまで、息子と2人きりで夫は息子が寝てから帰ってくることがほとんどですが、それでもなんとか1人でこなせるようになってきました。
そして夫の仕事はシフト制なので、保育園が休みの日に仕事といことも相変わらずありますが、土日どちらかは休みになるよう調整してくれたり、夫の仕事の日は両親が遊びに来てくれたりと、今も周りに助けられながら育児をしています。
「産後うつ」「不安障害」のような精神疾患には、「完治」というのはなかなか難しいかもしれませんが、これからも無理をしないで周りに助けてもらいながら育児をしていけたらと思います。